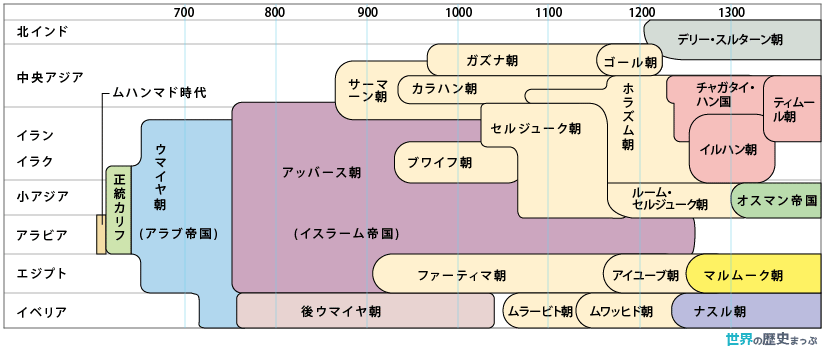正統カリフ時代のイスラーム国家
作成日:2023/10/9
アブー=バクル
人物
アラビア半島西部の都市
マッカ(メッカ)に住む
アラブ人のクライシュ族に属するタイム家の出身。
ムハンマドの親戚でもある。
アブー・バクルという
クンヤで専ら呼ばれるが、
偶像崇拝時代
ムスリムになる前もともとの彼の名前はアブドゥル=カアバ(カアバの奴隷。‘Abd al-Ka‘ba)であった。
ただしイスラームは一神教で、そして
カアバは神様でなくアッラーが定めた
ムスリム達の団結のシンボルで、
イスラームは偶像崇拝を否定していた。
そして彼の名前は偶像崇拝を招く意味があったのでイスラームに改宗したときに預言者
ムハンマドによって
ムハンマドの父の名前と同じアブドゥッラー(アッラーの奴隷。‘Abd Allāh )に改めたと伝えられている。
「美顔の持ち主」ゆえに「アティーク」とあだ名され(後世には同じ単語の別の意味から「(地獄の業火から)解放された者」と解釈された)、
また、最初期からのムスリムで信仰心篤く、
いかなる機会や事態に陥っても信仰を疑わず、
ムハンマドがミーラージュ(アラビア語版、英語版)の奇跡を語った時も真実としてこれを信じたため、
「非常に誠実な者」すなわちスィッディークという尊称(ラカブ)で呼ばれるようになった。
スィッディークは能動分詞サーディクの強意語形で常に言行が一致して誠実・嘘を言わず例外なく正直な人物を指すが、
アブー・バクルの場合はムハンマドのことを一切疑わず誠実に接して従ったことからついた通称である。
正統カリフまでの経緯
預言者である
ムハンマドの親友で、
ムハンマドの近親を除く最初の入信者であったとされる。
ムハンマドによる
イスラーム教の勢力拡大に貢献した。
娘のアーイシャを
ムハンマドに嫁がせたため、
ムハンマドの義父にもあたる(ただし年齢は
ムハンマドより3歳程度若い)。
西暦632年、
ムハンマドが死去した後、
選挙(信者の合意)によって初代
正統カリフに選出された。
選出に先立って最初期からの最有力の教友で同僚でもあったウマル・ブン・アル=ハッターブとアブー・ウバイダ・アル=ジャッラーブのふたりが、
アブー・バクルを預言者
ムハンマドの後継者である代理人(
カリフ、ハリーファ)として強力に推して人々に支持を求めて働きかけたため、
初代
カリフとなった。
アブー・バクルは
ムハンマドの死後、
イスラム共同体全体の合議によって
ムスリムたちの中から預言者
ムハンマドの代理人(ハリーファ)として共同体全体を統率する指導者(イマーム)、
すなわち「
カリフ(ハリーファ・アル=ラスールッラーフ)」として選出された。
このようにして選ばれたのは、
アブー・バクルを
嚆矢としてその後に続くウマル、
ウスマーン、アリーの4人であった。
アリー以降はイスラーム共同体内部の対立によってシリア総督となっていたムアーウィヤが共同体全体の合意を待たずに事実上実力で
カリフ位を獲得し、
イスラーム共同体最初の世襲王朝であるウマイヤ朝の始祖となった。
そのため、アブー・バクル、ウマル、ウスマーン、アリーの4人を指して、
スンナ派では伝統的に「正統カリフ」al-Khulafā' al-Rāshidūn (「正しく導かれた代理人たち」)と呼んでいる。(後述のように、
シーア派ではほとんどの場合、アリー以外の預言者
ムハンマドからの
イスラム共同体の教導権(イマーム権)・代理権(
カリフ権)の継承を否定している。)
正統カリフとしてのアブー・バクル
カリフとなったアブー・バクルは、
「
ムハンマドは死に、蘇ることはない」「
ムハンマドは、神ではなく人間の息子であり、
崇拝の対象ではない」
と強調した。
しかし、かつて
ムハンマドに忠誠を従ったアラブ諸族の中には、
その忠誠は
ムハンマドとの間で結ばれた個人的契約であるとして、
アブー・バクルに忠誠をみせない勢力もあった。
アブー・バクルはハーリド・イブン=アル=ワリードらの活躍によってこうした勢力を屈服させ、
ムスリム共同体の分裂を阻止した(リッダ戦争)。
また、イスラーム勢力拡大のためにサーサーン朝ペルシャや東ローマ帝国と交戦したが、
こうした戦争を通じて
ムスリム共同体の結束を強める狙いもあったと推測される。
アブー・バクルは、
カリフ在位わずか2年にして病のため亡くなった。
そのため、一連の征服活動は2代
カリフのウマル・イブン・ハッターブに受け継がれることになった。
スンナ派、シーア派での評価
アブー・バクルは
スンナ派では理想的な
カリフの一人として賞賛されている。
一方、
シーア派では本来預言者
ムハンマドの後継者であるべきだったアリーの地位を簒奪したとして、
批判の対象となることもあるが、
アリー本人はアブー・バクル、次はウマル、
次はウスマーンの下でカージー(最高裁判長)として任務を果たした。
こうした齟齬から、
彼を含む歴代
カリフたちの行った対外戦争は
ジハードの要件を満たしていないという見解がある。
ウマル・イブン・ハッターブ
ウマル・イブン・ハッターブ(ʿUmar ibn al-Khattāb)
西暦592年? -
西暦644年11月3日
初期
イスラム共同体の指導者のひとりで、
第2代
正統カリフ(
西暦634年 -
西暦644年)。
アラビア語での実際の発音:ウマル・ブヌ・ル=ハッターブ
分かち書きの場合の発音: ウマル・イブン・アル=ハッターブ
日本では
アラブ人名の定冠詞アルを除去してカタカナ表記する慣習があるため、
本来のウマル・イブン・アル=ハッターブではなくウマル・イブン・ハッターブと書かれていることが一般的である。
生い立ち
アラビア半島西部の都市
マッカ(メッカ)に住む
アラブ人のクライシュ族に属するアディー家の出身で、
若い頃は武勇に優れた勇士として知られていた。
西暦610年頃、
クライシュ族の遠い親族である
ムハンマド・イブン・アブドゥッラーフが
イスラーム教を開くと、
ウマルはクライシュ族の伝統的信仰を守る立場からその布教活動を迫害する側に回った。
伝えられるところによれば、
血気盛んな若者であったウマルはある日怒りに任せて
ムハンマドを殺そうと出かけたが、
その道すがら自身の妹と妹婿がイスラームに改宗したと聞き、
激怒して行き先を変え、
妹の家に乗り込んで散々に二人を打ちすえた。
しかし、ウマルは兄の前で妹が唱えたクルアーン(コーラン)の章句に心を動かされて改悛し、
妹を許して自らもイスラームに帰依した。
ウマルが
ムスリム(イスラーム教徒)となると、
クライシュ族の人々はウマルの武勇を怖れて
ムハンマドに対する迫害を弱め、
またマッカで人望のあるウマル一家の支援はマッカにおいて最初期の布教活動を行っていた
ムハンマドにとって大いに助けとなったといわれている。
西暦622年に
ムハンマドら
ムスリムがマッカを脱出し、
ヤスリブ(のちのマディーナ(メディナ))に移住するヒジュラ(聖遷)を実行したのちは、
マディーナで樹立された
イスラム共同体の有力者のひとりとなり、
イスラム共同体とマッカのクライシュ族の間で行われた全ての戦いに参加した。
また、夫に先立たれていたウマルの娘ハフサは
ムハンマドの4番目の妻となっており、
ムハンマドの盟友としてウマルは重要な立場にあったことがうかがえる。
ムハンマドの死から
西暦632年に
ムハンマドが死去すると、
マディーナではマッカ以来の古参の
ムスリム(ムハージルーン)とマディーナ以降の新参の
ムスリム(アンサール)の間で後継指導者の地位を巡る反目が表面化したが、
ウマルは即座に
ムハンマドの古くからの友人でムハージルーンの最有力者であったアブー・バクルを後継指導者に推戴して反目を収拾し、
マッカのクライシュ族出身の有力者が「神の使徒の代理人」を意味するハリーファ(
カリフ)の地位を帯びて
イスラム共同体を指導する慣行のきっかけをつくった。
アブー・バクルが2年後の
西暦634年に死去するとその後継者に指名され、
第2代目の
カリフとなる。
2代目カリフとして
ウマルは当初「神の使徒の代理人の代理人」(ハリーファ・ハリーファ・ラスールッラー)を名乗る一方、
後世
カリフの一般的な称号として定着する「信徒たちの指揮官」(アミール・アル=ムウミニーン)の名乗りを採用した。
また、ヒジュラのあった年を紀元1年とする現在のイスラーム暦のヒジュラ紀元を定め、
クルアーンと
ムハンマドの言行に基づいた法解釈を整備して、
後の時代にイスラーム法(シャリーア)にまとめられる法制度を準備した。
伝承によると、「信徒の指揮官」という称号は、
彼の治世時代に教友のひとりがたまたま口にした言葉をウマルが非常に好ましい名称と思い、
採用したと伝えられる。
彼をこのように呼んだ最初の人物は預言者
ムハンマドの従兄弟のアブドゥッラー・ブンジャフシュとも、
アブー・バクルと同じタイム家の重鎮ムギーラ・イブン・シュウバとも、
アムル・イブン・アル=アースとも言われている。
政治の面では、
アブー・バクルの時代に達成されたアラビア半島のアラブの統一を背景に、
シリア、イラク、エジプトなど多方面に遠征軍を送り出してアラブの大征服を指導した。
当時この地方では東のサーサーン朝と西の東ローマ帝国とが激しく対立していたが、
長期にわたる戦いによって両国ともに疲弊しており、
イスラーム帝国はその隙をついて急速に勢力を拡大しつつあった。
すでにアブー・バクル期末の
西暦633年には
メソポタミア地方に兵を出し、
フィラズの戦いにおいてサーサーン朝に痛撃を与えていた。
このような情勢下、
イスラーム軍は
西暦635年9月には東ローマ領だった
ダマスカスを占領し、
さらに、
西暦636年8月20日には東ローマの援軍をハーリド・イブン・アル=ワリードの指揮の元でヤルムークの戦いで撃破し、
シリアで東ローマとサーサーン朝の連合軍をも打ち破り、
シリアを制覇した。
西暦636年11月にはカーディシーヤの戦いによってふたたびサーサーン朝を撃破し、
西暦637年7月にはサーサーン朝の首都クテシフォンを占領。
西暦639年にはアムル・イブン・アル=アースに命じて東ローマ領のエジプトに
侵攻し、
西暦642年にはアレキサンドリアを陥落させてエジプトを完全に自国領とした。
西暦642年????643年????にはイランに進んだ
ムスリム軍がニハーヴァンドの戦いに勝利し、
ヤズデギルド3世率いるサーサーン朝を壊滅状態に追い込んだ。
西暦644年にはキレナイカまで進撃し、
ここをイスラーム領としている。
征服した土地では、
アラブ人ムスリム優越のもとで非
ムスリムを支配するために彼らからハラージュ(地租)・ジズヤ(非改宗者に課せられる税)を徴収する制度が考案され、
各征服地にはアーミル(徴税官)が派遣される一方、
軍事的な抑えとしてアミール(総督)を指揮官とする
アラブ人の駐留する軍営都市(ミスル)を建設された。
ウマルの時期に建設されたミスルとしては、
イラク南部のバスラ(
西暦638年)やクーファ(
西暦639年)、
エジプトのフスタート(現カイロ市南部、
西暦642年)などがある。
ウマルはミスルを通じて張り巡らされた軍事・徴税機構を生かすための財政・文書行政機構としてディーワーン(行政官庁)を置き、
ここを通じて徴税機構から集められた税をアター(俸給)として
イスラム共同体の有力者やアラブの戦士たちに支給する中央集権的な国家体制を築き、
歴史家によって「アラブ帝国」と呼ばれている、
アラブ人主体のイスラーム国家初期の国家体制を確立した。
西暦638年には首都のマディーナを離れて自らシリアに赴き、
前線で征服の指揮をとった。
同じ年、ウマルは
ムスリムによって征服されたエルサレムに入り、
エルサレムが
イスラム共同体の支配下に入ったことを宣言するとともに、
キリスト教のエルサレム総主教ソフロニオスと会談して、
聖地におけるキリスト教徒を庇護民(ズィンミー)とし、
彼等がイスラームの絶対的優越に屈服しジズヤを支払う限りに於いて一定程度の権利を保障することを約束した。(ウマル憲章)
また、このときにユダヤ教徒にも庇護民の地位が与えられ、
このときからエルサレムにおいて
イスラーム教、キリスト教、ユダヤ教の3つの宗教が共存するようになった。
このとき、エルサレムの神殿の丘に立ち入ったウマルは、
かつて生前の
ムハンマドが一夜にしてマッカからエルサレムに旅し、
エルサレムから天へと昇る奇跡を体験したとき、
ムハンマドが昇天の出発点とした聖なる岩を発見し、
そのかたわらで礼拝を行って、
エルサレムにおいて
ムスリムが神殿の丘で礼拝する慣行をつくったとされる。
この伝承に従い、ウマイヤ朝時代にこの岩を覆うように築かれた岩のドームは、
通称ウマル・モスクと呼ばれる。
またウマルはソフロニオスから神への祈りを共にするよう誘われたが、
ムスリムとして先例を残す事を好まずそれを断ったとされている。
ジハード、死
西暦644年11月、
ウマルはマディーナのモスクで礼拝をしている最中に、
個人的な恨みをもったユダヤ人ないしペルシャ人の奴隷によって刺殺された。
この奴隷はウマルの奴隷ではなく、
教友のひとりでウマルによってバスラ、クーファの長官となっていたアル=ムギーラ・イブン・シュウバの奴隷(グラーム)のアブー・ルウルウであった。
殺害の動機はウマルがハラージュ税を定めた時に彼の主人にも課税されたためこれを恨んだからであったという。
ウマルはこの時6ケ所を刺される重傷を負い、
3日後に非業の死を遂げた。
ウマルはマディーナにある預言者のモスクに葬られた。
伝承によると、アブー・ルウルウは彼自身その場で取り押さえられて報復として殺害されているが、
この時彼はモスク内で詰め寄ってきた人々をさらに11人刺しており、
内9名が死亡するという大惨事となった。
ウマルは刺された後、死の直前に後継の
カリフを選ぶための、
ウスマーン、アリー、タルハ・イブン・ウバイドゥッラー、
アッ=ズバイル・イブン・アル=アッワーム、
アブドゥッ=ラフマーン・イブン・アウフ、
サアド・イブン・アビーワッカースの6人からなる有力者会議(シューラー)のメンバーを後継候補として指名し、
さらにアンサールのアブー・タルハ・ザイド・イブン・サフルに命じて他のアンサールから50人の男を選んで、
彼らの6人から一人を選ぶようにも命じた。
このような経過の末ウマルの死の後、
互選によってウスマーン・イブン・アッファーンが第3代
カリフに選出された。
スンナ派、シーア派の評価
スンナ派では、
ウマルは理想的な政治を行った指導者として非常に尊敬されている。
もともと迫害側の有力者であったウマルの改宗は、
ヒジュラ前の初期の
イスラム共同体にとって大きな転機となったので、
ウマルは
ムスリムからは「ファールーク」(「真偽を分かつ者」)と呼ばれる。
しかし、
ムハンマドの娘婿であり第4代
カリフであるアリーのみが正統な
ムハンマドの後継者であると主張する
シーア派においては、
アブー・バクルとともにアリーが継承すべき指導者の地位を簒奪したとみなされ、
呪詛の対象となることもある。
なお、ウマルは
カリフとしてウマル1世と呼ばれることもあるが、
これは後のウマイヤ朝第8代
カリフ、ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズ(ウマル2世)と区別するためである。
ウスマーン・イブン・アッファーン
ウスマーン・イブン・アッファーン
テンプレートかな
| 在位 | : | 西暦644年 - 西暦656年 |
| 生年 | : | 西暦574年 or 西暦576年 |
| 没年 | : | 西暦656年6月17日 |
| | | |
| 父親 | : | アッファーン・イブン・アビー・ |
| | | アル=アース |
| 母親 | : | ウルワ・ビント・クライズ |
| 配偶者 | : | ルカイヤ、 |
| | ウンム・クルスーム、 |
| | ウンム・アムル・ビント・ジュンダブ、 |
| | ファーティマ・ビント・アル=ワリード |
| | | |
ウスマーン・イブン・アッファーンは、
イスラームの第3代正統カリフ。
マッカ(メッカ)のクライシュ族の支族であるウマイヤ家の出身。
預言者
ムハンマドの教友(サハーバ)で、
ムハンマドの娘婿にあたる。
ムハンマドの妻ハディージャを除いた人間の中では、
ウスマーンは世界で2番目にイスラームに入信した人物として数えられている。
クルアーン(コーラン)の読誦に長けた人物として挙げられることが多い7人の
ムハンマドの直弟子には、
ウスマーンも含まれている。
西暦651年頃、
ウスマーンの主導によって、
各地に異なるテキストが存在していたクルアーンの版が統一される。
西暦656年にウスマーンは反乱を起こした兵士によって殺害され、
その死はイスラーム史上初めて
カリフが同朋の
イスラム教徒に殺害された事件として記憶された。
莫大な財産を有していたことから、
ウスマーン・ガニー(「富めるウスマーン」の意)と呼ばれた。
また、
ムハンマドの2人の娘と結婚していたことから、
ズンヌーライン(「二つの光の持ち主」)とも呼ばれる。
生涯
イスラームへの帰依前
ウマイヤ家の豪商アッファーン・イブン・アビー・アル=アースとアルワ(ウルワー)の子として、
ウスマーンは生まれる。
母のウルワは預言者
ムハンマドの従姉妹にあたる。
ウスマーンの幼年期については、不明な点が多い。
子供のころに厳格な教育を受けたと思われ、
マッカに住む若者の中でも特に読み書きに長けた人間に成長した。
幼少のウスマーンが他の
アラブ人の子供に混ざって脱いだ服に石を集めて運ぶ遊びをしていた時、
何者かに「服を着よ、肌を出してはならない」と言われてすぐに遊びを止めて服を着、
以来人前で服を脱ぐことは無くなったという伝承が残る。
ウスマーンが20歳になった時、父のアッファーンが旅先で客死し、
ウスマーンは父の遺した莫大な財産を相続した。
父と同様に交易に携わったウスマーンは事業で成功を収め、
跡を継いだ数年後にはクライシュ族内でも有数の富豪になっていた。
商売で不正を行うことは無く、
慎重かつ公正な姿勢を心掛けていた。
イスラームへの改宗
ウスマーンが改宗した理由について、
彼が
ムハンマドの娘のルカイヤに恋焦がれていたためだと言われている。
ウスマーンは密かにルカイヤを想っていたが
ムハンマドに結婚を言い出す事が出来ず、
ルカイヤは
ムハンマドの従兄弟ウトバの元に嫁いだ。
叔母のスウダーに相談したウスマーンは、
やがて
ムハンマドに重大な出来事が起こり、
その時にはルカイヤが自分の下に嫁ぐと言われ、
叔母からの助言を心に留め置いた。
西暦610年初頭、
ウスマーンは旅先でマッカに預言者が現れた声を聞き、
マッカに戻ったウスマーンは友人のアブー・バクルの勧めを受けて
ムハンマドに帰依した。
クライシュ族内ではウマイヤ家と
ムハンマドが属するハーシム家の対立が深まり、
ウマイヤ家の人間はウスマーンが
ムハンマドの教えに入信したことを喜ばなかった。
ウマイヤ家の家長であるアル=ハカムはウスマーンを縛り付けて棄教を迫り、
母のアルワと継父のウクバからも棄教を説得された。
それでもウスマーンの決意を翻すことはできず、
アル=ハカムはウスマーンをクライシュ族の信仰に立ち返らせることを諦め、
アルワはウスマーンを勘当した。
スウダーはウスマーンを擁護し、
ウスマーンの異父妹であるウンム・クルスームは兄に続いてイスラームに改宗した。
ムハンマドがハーシム家の人間から迫害を加えられた時、
ウトバ親子も
ムハンマドを責めて、
ルカイヤは
ムハンマドの下に帰された。
また、ウスマーンはイスラームの教えを拒否する二人の妻と離婚した。
ウスマーンが離婚したことを知ったアブー・バクルは、
ムハンマドにウスマーンとルカイヤの結婚を提案する。
ムハンマドはクライシュ族の有力家系であるウマイヤ家の人間の改宗を喜び、
ルカイヤをウスマーンの元に嫁がせて友好関係の継続を望んだ。
ウスマーンとルカイヤは幸福な結婚生活を送っていたが、
クライシュ族内でのイスラーム教徒への迫害は激しさを増し、
ウスマーンは
ムハンマドと話し合った末、
交易でつながりのあったエチオピアへの避難を決定した。
西暦615年、
ウスマーン夫妻は信徒を連れてエチオピアに移住する。
移住先のエチオピア王国では歓迎を受け、
マッカ時代と同じように交易を続け、
貧窮した人間に援助を与えた。
また、エチオピア滞在中にルカイヤとの間に男子が生まれ、
ウスマーンは息子にアブドゥッラーと名付けた。
移住から2年後にマッカのクライシュ族が
イスラーム教を受け入れた報告を受け取り、
ウスマーン夫妻は何人かの信徒を連れてマッカに帰国した。
帰国後、報告が誤りだと分かった後もウスマーンたちはマッカに留まり続け、
迫害に耐え続けた。
ムハンマドの家族とハーシム家の人間がマッカ郊外の渓谷に追放された時、
ウスマーンは
ムハンマドたちに食糧を供給し続けた。
同時に
ムハンマドたちへの制裁の廃止をクライシュ族の若者たちに説き、
ムハンマドへの制裁は中止される。
西暦622年のヒジュラに際し、
ウスマーンも他の信徒と同じようにヤスリブ(後のマディーナ、メディナ)に移住する。
ヒジュラ後
マディーナで新たな生活を始めたウスマーンは、
ユダヤ教徒に独占されている商行為にイスラーム教徒も参入するべきだと考え、
マッカから運び込んだ財産を元手に商売を始める。
ウスマーンはマディーナでも慈善事業に携わり、
ムハンマドの邸宅とモスク(寺院)の建立に必要な土地を購入する資金を捻出した。
また、水の確保にも尽力し、
ユダヤ教徒と交渉し邸宅の権利を買い取ることができた。
西暦624年頃にマディーナで天然痘が流行し、
ルカイヤは天然痘に加えてマラリアに罹る。
西暦624年のバドルの戦いでは、
ウスマーンは従軍を志願したが、
ムハンマドは自分の代理としてマディーナに残り、
ルカイヤの看病をするように命じた。
バドルでイスラーム軍とクライシュ族が交戦している時にルカイヤは病没し、
マディーナに勝利の知らせが届いたときには彼女の埋葬は終えられていた。
バドルの戦いから1年が経過した後もウスマーンはルカイヤを亡くした悲しみから立ち直れず、
またウフドの戦いで誤報を信じて退却したことを悩んでいた。
西暦625年末、
ムハンマドはウスマーンを慰めるため、
ルカイヤの妹であるウンム・クルスームを彼に娶わせた。
翌
西暦626年にアブドゥッラーを亡くし、
西暦630年にウンム・クルスームも早世する。
西暦628年3月に
ムハンマドが
カアバ神殿巡礼のためにマッカに向かった時、
同行したウスマーンはマッカのクライシュ族との交渉役を任せられる。
交渉の後、
ムハンマドとマッカの間に和約が成立した(フダイビーヤの和議)。
和議はクライシュ族にとって一方的に有利な内容になっていたため、
イスラム教徒の中には和議に不服な人間も多かったが、
ウスマーンはクライシュ族の中に
イスラム教徒が増えてやがて事態は好転すると考えていた。
ウスマーンの予測は当たり、
クライシュ族内の有力者にイスラームに改宗する者が多く現れる。
信徒の増加に伴うマディーナのモスクの増築にあたっては、
ウスマーンは工事費の全額を負担し、
自らもレンガを運んで工事に参加した。
西暦632年6月9日に
ムハンマドが没し、
マディーナでその知らせを聞いたウスマーンは憔悴するが、
アブー・バクルの励ましを受けて立ち直る。
アブー・バクルが
カリフに就任した後、
ウスマーンはウマルの次にバイア(忠誠の誓い)を示した。
厳格なウマルが
カリフに就任した後、
ウマルは自分に正面から意見をするウスマーンに信頼を置いていた。
ウスマーンは若者の多い
イスラム教徒の間で温厚な人物として尊敬を受けていたが、
ウマルの治世の末期まで目立った動向は無かった。
ウスマーンは政治顧問としてマディーナに留まり、
ウンマ(
イスラム共同体)の運営に従事していた。
カリフ即位後
ウスマーンは死に瀕したウマルから後継者候補の一人に指名され、
同じく後継者候補に指名されたアリー、
タルハ、
ズバイル、
アブドゥッラフマーン・イブン・アウフ、
サアド・イブン・アビー・ワッカースらクライシュ族出身のムハージルーン(マッカ時代からの
ムハンマドの信徒でマディーナに移住した人間)の長老と会議(シューラー)を開いた。
カリフの候補者はウスマーンとアリーに絞られ、
アウフが議長を務めた。
ウマルが没してから3日間、
アウフは指導者層以外のマディーナの人間にもいずれが
カリフに適しているかを諮り、
最終的にウスマーンを
カリフの適格者に選んだ。
西暦644年11月7日、
ウスマーンはマディーナのモスクでバイアを受け、
カリフに即位する。
ウスマーンは
カリフという職務に強い重圧を感じ、
最初の演説を行うために説教台に登った彼の顔色は悪く、
演説はたどたどしいものとなったと伝えられている。
クライシュ族の長老たちにはウスマーンの支持者が多く、
アリーの主な支持者であるアンサール(ヒジュラより前にマディーナに住んでいた
イスラム教徒)には発言権が無かったことが、
ウスマーンの
カリフ選出の背景にあったと考えられている。
さらに別の説として、
ウマル時代の厳格な統治からの脱却を望んだ多くの人々が、
禁欲的な生活を求めるアリーではなく、
ウスマーンを支持したためだとも言われている。
史料の中には、
他の長老からの「先任の二人の
カリフの慣行に従うか」という質問に、
ウスマーンは「従う」と断言し、
アリーは「努力する」と答えたことが選出の決め手になったと記したものもある。
西暦645年頃、
ウマルの死が伝わるとイスラーム勢力への反撃が各地で始まり、
アゼルバイジャンとアルメニアでは部族勢力の反乱が起こり、
エジプト・シリアの地中海沿岸部は東ローマ帝国の攻撃を受ける。
ウスマーンはそれらの土地の騒乱を鎮圧し、
中断されていたペルシャ遠征を再開した。
ニハーヴァンドの戦いの後に進軍を中止していた遠征軍は、
ウスマーンの命令を受けて進軍を再開した。
西暦650年にジーロフトに到達した遠征軍は、
三手にわかれてマクラーン、スィースターン(シジスターン)、ホラーサーンを征服し、
ペルシャの征服を完了する。
翌
西暦651年にメルヴに逃亡したペルシャの王ヤズデギルド3世は現地の総督に殺害され、
サーサーン朝は滅亡した。
シリアからは
メソポタミア北部への遠征軍が出発し、
西暦646年にアルメニア、
西暦650年にアゼルバイジャンを征服する。
こうして、
ムハンマドの時代から始まった
アラブ人の征服活動は、
西暦650年に終息する。
ウスマーンは
カリフとして初めて中国に使者を派遣した人物と考えられており、
西暦651年に唐の首都である長安にイスラーム国家からの使者が訪れた。
治世の後半、エジプトやイラクではウスマーンの政策への不満が高まった。
シリアにはウマルの時代に総督に任命されたムアーウィヤを引き続き駐屯させ、
エジプトにはウスマーンの乳兄弟であるイブン・アビー・サルフが総督として配属された。
ウスマーンが実施したウマイヤ家出身者の登用政策は一門による権力の独占として受け取られ、
イスラム教徒の上層部と下級の兵士の両方に不満を与えた。
バスラやクーファに駐屯する兵士は俸給の削減によって苦しい生活を送り、
地方公庫からの現金の支給を要求したが、
総督は彼らの要求を容れなかった。
ウスマーンの治世の末期には、
反乱とウスマーンの暗殺が計画されている噂が流れていた。
最期
西暦654年にウスマーンは各地の総督をマディーナに招集して政情について討議を重ね、
ムアーウィヤからシリアに避難するように勧められたが、
ウスマーンは避難と護衛の派遣を拒否してマディーナに留まった。
西暦656年バスラ、
クーファ、
エジプトの下級兵士は総督の不在に乗じて連絡を取り合い、
マディーナに押し寄せた。
ウスマーンはディーワーン職に就いていたマルワーンと改革派からの批判の対象となっている統治官の解任を条件に
ムハンマドの従兄弟アリーに助けを求め、
アリーは兵士たちを説得して彼らを帰国させた。
しかし、数日後に兵士たちはマディーナに戻り、ウスマーンの退位を要求した。
モスクでの説教と礼拝はウスマーンの支持者と反乱者の衝突の場となり、
礼拝に現れたウスマーンに石が投げつけられる事件が起きる。
数百人の反乱者はウスマーンの邸宅を取り囲んで方針の転換を要求し、
ウスマーンの政策に不満を抱くマディーナの住民は彼を助けようとしなかった。
ウスマーンはイスラームとマディーナの守護のために各地の総督に援軍の派遣を要請し、
またウスマーンの元を訪れた教友たちは反乱者の討伐、
あるいは亡命を進言したが、
ウスマーンは攻撃を拒んで邸宅に残った。
6月17日、兵士たちは彼の邸宅に押し入り、
包囲の中でもウスマーンはクルアーンを読誦していた。
アブー・バクルの子
ムハンマドが最初にウスマーンを切りかかり、
ウスマーンは切りつけられながらもなおクルアーンの読誦を続けていた。
深手を負った後もウスマーンはなおクルアーンを抱きかかえ、
クルアーンは彼の血で赤く染まったという。
ウスマーンを殺害した兵士たちは、国庫から財産を奪って逃走した。
ウスマーンの遺体は、
殺害当日の日没の礼拝と夜の礼拝の間の時間にマディーナのハッシュ・カウカブに密かに埋葬される。
ウスマーンの墓の側には、
彼を助けようとして殺害された召使いのサビーフとナジーフの遺体が埋葬された。
ハッシュ・カウカブは墓地であるバギーウの東に位置し、
ハッシュ・カウカブを買い上げたウスマーンはこの場所が将来墓地となることを予見していたが、
彼自身が最初に墓地に埋葬された人間となった。
ムアーウィヤはウマイヤ朝の建国後にハッシュ・カウカブのウスマーンの墓を詣で、
土地の周りを取り囲んでいた壁を壊して、
この地を墓地にするように命令した。
また、ウスマーンが読んでいたと伝えられるクルアーンの写本は、
タシュケント(ウスマーン写本)、
イスタンブールのトプカプ宮殿(トプカプ写本)に保管されている。
没時のウスマーンの年齢は80歳、85歳、
あるいは
イスラム教徒にとって重要な年齢である63歳と諸説ある。
歴史家のマスウーディーはウスマーンが没した時、
彼の財産として東ローマの金貨100,000ディナール、
ペルシャの銀貨1,000,000ディルハム、100,000ディナール相当の邸宅、
私有地、多くの馬とラクダが遺されていたと記述している。
ウスマーンの殺害について、
正統な権力の拒絶である故意の殺人で極刑に処すべきだとする意見、
地位を乱用した人間に処刑を下したに過ぎないという意見が出され、
二つの立場の議論は形を変えて数百年の間続けられた。
このため、ウスマーンの死はイスラームの政治理論と実践に大きな影響を与えたと考えられている。
政策
ウスマーンは政策を決定する場合には、
古参の信徒や有識者からなる委員の合議にかけて意見を聞いていた。
アラブ人は短期間で広大な支配地を獲得したものの、
統一された支配体制は未だに確立されていなかった。
行政の円滑化と中央集権化を推進するため、
ウスマーンは自身の出身であるウマイヤ家の人間を中央・地方の要職に抜擢し、
彼がとった縁故主義は批判に晒された。
ウスマーンによるウマイヤ家出身者の起用に対し、
ムハンマドの寡婦アーイシャは、
ムハンマドの形見の衣服がそのまま残っているほど時間が経っていないのに、
ウスマーンはスンナを忘れたのかと批判した。
アリーは、
トラカーウ(
西暦630年の
ムハンマドのマッカ征服に際してイスラームに改宗した人間)であるウマイヤ家出身の総督が統治者にふさわしくないと考えていた。
ウマイヤ家出身の総督の解任を望む多くの教友に対し、
ウスマーンは総督たちの行状を確認するために古参の教友を各地に派遣し、
解任に相当する事由がない報告を受け取った。
西暦650年の征服戦争の終結は、
軍事行動に従事した兵士から戦利品による収入を絶ち、
兵士たちは政府から支給されるわずかな俸給で生活していかなければならなくなった。
兵士たちはマディーナで富と権力を独占するイスラーム教徒の上層部に不満を抱き、
彼らの第一人者であるウスマーンに憎しみが集中した。
東ローマ帝国との戦争に従軍することが予定されていたシリアの
アラブ人は税制と居住地の面で優遇を受けていたため、
彼らの中にはウスマーンとシリア総督を務めていたムアーウィアを支持する者が多かった。
しかし、クーファでは部族間・部族集団内での貧富の差が大きく、
征服活動が終息した後に町では激しい内紛が起きた。
ウスマーンは征服軍の兵数が不足するエジプトへの移住を推進し、
新旧の兵士の間に激しい衝突が起きた。
また、征服地の住民の中には、
マディーナから派遣されるクライシュ族にのみ統治が委ねられていることに不満を持つ者もいた。
ウスマーン時代に実施されたサワーフィー(
アラブ人がイラクで獲得した土地のうち、
皇帝、神殿、貴族の所有地を指して呼ばれた地域)の収入の変更について、
歴戦の民(シャイバーン族やマフズーム家のハーリド・イブン・アル=ワリード配下の兵士など、アラブの征服事業に初期から参加していた兵士)から反対の声が上がった。
従来はサワーフィーから上がる収益の80%が戦利品として土地の所有者の手に渡り、
残りの20%が
カリフの取り分とされていたが、
戦利品の減少によって収益の全てが
カリフの取り分とされた。
このため、
西暦655年にイラク総督は捕らえられ、
代わりに現地の事情に詳しいアブー・ムーサー・アル=アシュアリーが総督に擁立された。
イスラーム国家が獲得した莫大な富について、
ウスマーンは前任の
カリフ・ウマルと同様に、
イスラム教徒に危険な存在であると認識していた。
同時に財産は生活を富ませる事も出来るものだと捉えており、
入手方法と使用方法が合法的なものであれば、
一般の人々であっても享楽を楽しむことが許されると考えていた。
金銭の欲望を制御してきた自分自身の経験から、
ウスマーンはウマルのように金銭に対する欲望は際限のないものだと考えず、
彼の統治下では豪奢な生活を送ることが認められていた。
ウスマーンの時代に、
ウマイヤ家の総督を含む多くのウンマ(
イスラム共同体)の人々が奢侈を好むようになったと言われている。
こうした社会状況下でウスマーンが自分自身、
あるいは一門のために国庫の財産を流用している噂が流れたが、
真偽については判明していない。
ウスマーンの最大の事業として、
各地に様々な版が存在していたクルアーン(コーラン)の統一が挙げられる。
ムハンマドの存命中からクルアーンを書物の形にまとめる事業が続けられていたが、
ウスマーンの時代には少なくとも4種類のクルアーンのテキストが存在し、
文章と読み方は互いに異なっていた。
新たに改宗した非
アラブ人の間では、
それぞれが読むクルアーンの文が異なる問題が顕著になっていた。
ウスマーンはザイド・イブン・サービトを中心とする委員にクルアーンの「正典」を編集させ、
他の版をすべて破棄させた。
後世に作成されたクルアーンは、
すべてウスマーン版のクルアーンに合致するものとされている。
ウスマーンの編纂事業より前に成立したクルアーンの中には廃棄を逃れたものもあり、
イブン・アビー・ダーウードらによってクルアーン解釈学の資料として用いられた。
当時の人間からは不信仰にあたる行いとして激しい非難を受け、
ウスマーンを嫌った後世の人間はアブー・バクルがクルアーンを統一した伝承を作り上げた。
だが、思想を異にする多くの分派、神学者、法学者が用いるクルアーンの内容が統一されたことで、
ウンマ(
イスラム共同体)やイスラーム法の一体性が確保された。
さらに、政治・信条を巡る議論の正典への波及を防ぎ、
共通の議論の場が提供されたことで、
イスラーム文明に安定と発展がもたらされた。
また、ウスマーンの時代にはイスラーム国家の海軍が整備された。
ウマルの時代に海軍の増強は行われなかったが、
度重なる東ローマ軍のエジプトへの攻撃に対して、
シリア総督ムアーウィヤから艦隊の創設が提案された。
協議を経て、シリア人とエジプト人からなるアラブ発の艦隊が編成された。
西暦654年/
西暦655年に、
エジプト、シリアから出港した艦隊はリュキア沖のマストの戦い(サーワーリーの戦い)で東ローマ艦隊に勝利を収め、
東地中海の制海権を掌握する。
人物像
ウスマーンは謙虚な性格の人物で、自慢する事を嫌い、
自分の考えを他人に強制しようとしなかった。
若年期のウスマーンは果実酒と賭け事を遠ざけて、
若者たちのふざけ合いにも加わらない、
倫理が失われていた当時のマッカで節度を保った生活を送っていた。
カリフとなった後も粗末な衣服を着て一般の信徒に混ざってモスクで昼寝をし、
財産の多くを困窮した人間の救済に充てていた。
毎週の金曜日には奴隷を買い取り、
彼らを奴隷身分から解放していたと伝えられている。
ウスマーンの行動は、
寛大な性格と神と
ムハンマドに対する羞恥心に基づいていたと考えられている。
ムハンマドはウスマーンの寛大・謙虚な政策を称え、
ウンマの中で最も恥を知り、信頼のおける人物として挙げた。
だが、敬虔かつ潔癖なウスマーンには、
同族からの利益の要求を断れない弱さがあった。
ウスマーンは黄を帯びた白色の顔で、
見事な顎鬚を持つ気品のある容貌の人物だと伝えられている。
金の針金で歯を束ねて飾り立て、
顔にわずかに残っていた天然痘の跡はウスマーンの男性的な魅力をより高めていた。
優れた容貌と莫大な財産を持つウスマーンには多くの女性が近づいてきたが、
ウスマーンは妻以外の女性と関係を持つことは無かった。
ウスマーンは在位中に国家の混乱を収拾することができなかったため、
統治能力について否定的な評価を下されることが多い。
また、前任の
カリフであるアブー・バクルやウマルのような尊敬を集める事はできなかった。
他の3人の正統カリフと違ってウスマーンは軍事的実績には乏しいが、
資産を生かした軍事費の援助には誰よりも貢献していた。
西暦630年に東ローマ帝国からアラビア半島への遠征軍が派遣された時、
ウスマーンは軍費、軍用のラクダ、軍馬、食糧を供出してイスラーム軍を助けた。
家族
ジャーヒリーヤ時代、
ウスマーンはウンム・アムル・ビント・ジュンダブとファーティマ・ビント・アル=ワリードという2人の妻を娶っていた。
ウスマーンの継父であるウクバ・ビン・マヒートは最も激しく
イスラム教徒に圧迫を加えた人間の一人で、
ウクバが
カアバ神殿で礼拝を行っている
ムハンマドを絞殺しようとした時、
ウスマーンはアブー・バクルと共に身を挺して
ムハンマドを守った。
後にバドルの戦いで捕虜となったウクバが
ムハンマドから死刑を宣告されると、
ウクバはウスマーンに取り成しを頼んだが、
ウスマーンは温情をかけなかった。
西暦630年のマッカ征服の後、
ウスマーンの母アルワと彼の異父弟妹たちは多くのクライシュ族と同様にイスラームに帰依し、
ウスマーンと和解した。
ムハンマドはウスマーンとルカイヤの間に生まれた孫のアブドゥッラーを気に入り、
しばしばアブドゥッラーと一緒に礼拝を行っていた。
ルカイヤの死後に再婚したウンム・クルスームとの間に子供は生まれず、
アブドゥッラーの死後にウスマーンと
ムハンマドの姻戚関係は消滅する。
ムハンマドのウスマーンへの信頼は強く、
ムハンマドは「もし自分に3人目の娘がいれば、ウスマーンに嫁がせただろう」と述べた。
- 父母
-
- 父:アッファーン・イブン・アビー・アル=アース
- 母:アルワ・ビント・クライズ
- 義父:ウクバ・ビン・マヒート - アッファーンの死後、アルワと再婚
- 兄弟
-
- アムナー - 同父妹
- ワリード - 異父弟
- ハーリド - 異父弟
- アムル - 異父弟
- ウンム・クルスーム - 異父妹
- 妻子
-
-
ウンム・アムル・ビント・ジュンダブ
-
ファーティマ・ビント・アル=ワリード
-
ルカイヤ
-
Wikipedia原文:ウンム・サイード・ファーティマ・ビント・アル=ワリード・ビン・アブド・シャムス - ウンム・クルスームの死後に再婚
意味不明だが、想像すると・・・
「ウンム・サイード」、「ファーティマ・ビント・アル=ワリード」、「ビン・アブド・シャムス」、「ウンム・クルスーム」の死後に再婚
か?、にしても意味不明。
アリー・イブン・アビー・ターリブ
アリー・イブン・アビー・ターリブは、
イスラーム教の第4代正統カリフ。
イスラーム教シーア派の初代イマーム。
預言者
ムハンマドの父方の従弟で、
母も
ムハンマドの父の従姉妹である。
後に
ムハンマドの養子となり、
ムハンマドの娘ファーティマを娶った。
ムハンマドがイスラーム教の布教を開始したとき、
最初に入信した人々のひとり。
直情の人で人望厚く、
武勇に優れていたと言われる。
早くから
ムハンマドの後継者と見做され、
第3代正統カリフのウスマーンが暗殺された後、
第4代
カリフとなったが、
対抗するムアーウィヤとの戦いに追われ、
西暦661年にハワーリジュ派によって暗殺される。
のちにアリーの支持派は
シーア派となり、
アリーは
シーア派によって初代イマームとして
ムハンマドに勝るとも劣らない尊崇を受けることとなった。
アリーとファーティマの間の息子ハサンとフサインはそれぞれ第2代、
第3代のイマームとされている。
また、彼らの子孫はファーティマを通じて預言者の血を引くことから、
スンナ派にとってもサイイドとして尊崇されている。
アリーの墓廟はイラクのナジャフにあり、
カルバラーとともに
シーア派の重要な聖地となっている。
生涯
生い立ち
アリーは預言者
ムハンマド同様、
マッカ(メッカ)のクライシュ族のハーシム家に属す。
祖父は
ムハンマドと同じくアブドゥル=ムッタリブで、
父のアブー・ターリブは
ムハンマドの父アブドゥッラーの同母弟である。
つまり、アリーは
ムハンマドの父方の従弟にあたる。
また母も
ムハンマドの祖父の姪であった。
アリーは
西暦600年ないし
西暦602年頃に
マッカ(メッカ)で誕生した。
場所は父アブー・ターリブの家であったという説と、
カアバ神殿内であったという説がある。
日付はラジャブ月(イスラーム暦の7月)の13日と伝えられる。
伝承によれば母のファーティマ・ビント・アサドは初め彼の名を「ハイダラ」(獅子)と名づけようとしたが、
父のアブー・ターリブがそれを退けて「アリー」(高貴な人)という名をつけたとされる。
また別伝によれば、
ファーティマは「ハイダラ」、
アブー・ターリブは「ザイド」という名を考えていたが、
誕生を祝いに訪れた
ムハンマドが「アリー」と命名したという。
アリーが5歳のときにアブー・ターリブ一家が窮乏に陥ったため、
彼は
ムハンマドとハディージャの夫婦に引き取られて養子として育てられることになった。
青年時代
西暦610年頃に、
ムハンマドはアッラーの啓示をはじめて受けたという。
このときアリーは、
ムハンマドの妻ハディージャに次ぐ2番目の信者としてイスラームを受け入れたとされる。
以後アリーは
ムハンマドとともにイスラームの布教につとめるが、
ムスリムたちは度重なるマッカ市民の迫害により、
西暦622年にマディーナ(メディナ)への亡命(ヒジュラ)を強いられる。
ムハンマドがマッカを出発する頃にはすでに事態は切迫しており、
反対派は彼の殺害計画を練っていた。
アリーは
ムハンマドがマッカを脱出した夜、
刺客を欺くために身代わりとして
ムハンマドの寝床に横たわった。
やがて暗殺者たちが現われたが、
彼らは
ムハンマドの不在を知ると失望し、
アリーに危害を加えることもなく去った。
アリーは
ムハンマドの指示によって、
その後なお3日間にわたってマッカにとどまり、
ムハンマドが知人から預かっていた金をすべて精算してからマディーナへ向かったという。
ヒジュラ後、
アリーは
ムハンマドの片腕として教団の運営やジハード(聖戦)に携わった。
とくに戦場における活躍は目覚しく、
アリーはバドルの戦い、
ウフドの戦い、
ハンダクの戦いで次々に敵側の名高い勇士を倒し、
ハイバルの戦いではイスラーム軍の誰も陥すことができなかったハイバル砦を陥落させるなど、
勇将としての名声を次第に高めていった。
恋愛・婚姻関係
マディーナに移住した後、
西暦623年、
ムハンマドはアリーに、
娘のファーティマをアリーと結婚させるよう神が命じたと語った 。
この結婚は、
イスラーム教徒にとって、
ムハンマドの親戚の最も重要かつ神聖な人物たちの結びつきと見なされている。
ほぼ毎日娘を訪ねてきた
ムハンマドは、アリーに近づき、
「汝はこの世界でも来世でも私の兄弟である」と告げた。
ムハンマドはファーティマに「私はあなたを私の一家の最愛の者と結婚させた」と告げた。
アリーの家族は
ムハンマドから頻繁に称賛された。
彼らはまた、
「浄化のアーヤ」のような場合にクルアーンで栄光を与えられた。
一夫多妻制は許可されたが、
ファーティマが生きている間、
アリーは他の女性を妻としなかった。
ファーティマの死後、
アリーは他の女性と結婚し、
多くの子供をもうけた。
ムハンマドの死と継承問題
ムハンマドは
西暦632年に没し、
ウンマは最初の危機を迎えた。
ウィルファード・マデルングによれば、
アリーは
ムハンマドとの親密な関係と
イスラーム教に関する幅広い知識によって、
ムハンマドの後を継ぐのに最適な人物であると考えられていた。
そこで、
ムハンマドの晩年の妻アーイシャの父アブー・バクルが、
選挙(
ムスリムの合意)によって指導者に選ばれ、
ムハンマドの代理人を意味する
カリフ(ハリーファ)を名乗った。
アリーは若さを理由に外されたと言われている。
正統カリフたちの時代
アラビア半島の統一を達成したアブー・バクルは
西暦634年に病死し、
ムハンマドの妻の1人ハフサの父ウマルが後継者に指名された。
ウマルは中央集権的なイスラーム帝国を築き上げ、
西暦642年のニハーヴァンドの戦いでサーサーン朝を滅亡寸前に追い込んだが、
西暦644年に奴隷に刺されて重傷を負い、
死の床に有力者を集めて後継者を選ばせ、絶命した。
このときの後継候補にはアリーも含まれていたが、
後継
カリフに選出されたのは、
ムハンマドの2人の娘ルカイヤとウンム・クルスームを妻としていたウスマーンであった。
ウスマーンは、
西暦650年頃にクルアーン(コーラン)の正典(ウスマーン版)を選ばせ、
西暦651年にサーサーン朝を完全に滅亡させるといった功績を挙げた。
アブー・バクル、ウマル、ウスマーンと、
その次に
カリフとなったアリーの4代を、
正統カリフという。
ウスマーンの死とアリーのカリフ就任
しかし、ウスマーンは自分の家系であるウマイヤ家を重視する政策を採ったため、
クライシュ族の他の家系の反発を招き、
西暦656年に暗殺された。
次の
カリフ位をめぐって、
ムハンマドの従弟で娘婿のアリーと、
ウスマーンと同じウマイヤ家のムアーウィヤが争った。
紆余曲折を経て、アリーが第4代の
カリフに就任した。
ムアーウィヤとの対立
アリーが
カリフに就任するが、ムアーウィヤや、
ムハンマドの晩年の妻で初代正統カリフのアブー・バクルの娘アーイシャはこれに反発した。
西暦656年、
アリーはまずアーイシャの一派をラクダの戦いで退けた。
ムアーウィヤは、ウスマーンを暗殺したのはアリーの一派であるとして、
血の報復を叫んでアリーと戦闘に至った。
ムアーウィヤは、
西暦657年のスィッフィーンの戦いでアリーと激突した。
戦闘ではアリーが優位に立ち、
武勇に優れたアリーを武力で倒すことは難しいと考えたムアーウィヤは、
策略をめぐらせてアリーと和議を結んだ。
この結果、
ムアーウィヤは敗北を免れたことでウンマの一方の雄としての地位を確保し、
アリーは兵を引いたことで支持の一部を失うことになった。
ハワーリジュ派の登場
アリーがムアーウィヤと和議を結んだことに反発したアリー支持者の一部は、
ムアーウィヤへの徹底抗戦を唱えてアリーと決別し、
イスラーム史上初の分派と言われるハワーリジュ派(ハワーリジュとは「退去した者」の意)を形成した。
アリーの勢力弱体化
ムアーウィヤは、
西暦660年に自らカリフを称した。
ハワーリジュ派は、
アリー、ムアーウィヤとその副将アムル・イブン・アル=アースに刺客を送った。
アリーとその支持者は、
勢力を拡大し続けるムアーウィヤとの戦いに加えて、
身内から出たハワーリジュ派にも対処しなければならなくなり、
疲弊を余儀なくされた。
アリー自身はムハンマド存命中のウンマ防衛や異教徒侵略のための戦いで活躍したが、
それは多くが数百の手勢を率い、
自身も先頭に立って戦う野戦指揮官としてであり、
個人的な武勇や戦術を超えた、
数万の軍隊を指揮する戦略や有力な軍司令官や総督を引き込む政略では、
ムアーウィアにはるかに及ばなかった。
アリーの最期
ムアーウィヤは刺客の手から逃れたが、
一方アリーは西暦661年にクーファの大モスクで祈祷中にアブド=アルラフマーン・イブン・ムルジャムにより毒を塗った刃で襲われ、
2日後に息を引き取った。
正統カリフ4代のうち実に3代までが暗殺されたことになる。
アリーの暗殺により、ムアーウィヤは単独のカリフとなり、
自己の家系によるカリフ位の世襲を宣言し、
ウマイヤ朝を開くことになる。
これに反発したアリーの支持者は、
アリーとムハンマドの娘ファーティマとの子ハサンとフサインおよびその子孫のみが指導者たりうると考え、
彼らを無謬のイマームと仰いでシーア派を形成していく。
これに対して、ウマイヤ朝の権威を認めた多数派は、
後世スンナ派(スンニ派)と呼ばれるようになる。
シーア派の教義におけるアリー
シーア派では、アリーがムハンマドから直接後継者に任じられたとし、
アブー・バクル、ウマル、ウスマーンの3代の正統カリフの権威を認めない(彼らを簒奪者であるとして呪詛の対象とすることもある)。
そして、指導者として預言者ムハンマドの血を引くことを重視し、
ムハンマドの娘ファーティマとアリーとの間に生まれたハサン、
フサインの2人をそれぞれ第2代、
第3代のイマームとする(シーア派のうちカイサーン派のみは、アリーと別の妻ハウラとの子ムハンマド・イブン・ハナフィーヤを第2代のイマームとする)。
一般にハサンやフサインの血統の人々は、
特に「シャイフ」や「サイイド」と呼ばれ宗派を問わずムスリム社会では尊敬を受けるが、
サイイド自身も預言者の後裔として社会から尊敬を受けるべく身を律するよう求められており、
シーア派のみならずサイイド自身がウラマーやスーフィー教団のシャイフなど宗教的職権を担うことも一般的であった。
イドリース朝やファーティマ朝、
サファヴィー朝のように場合によってはムハンマドの後裔を称する人々が政権を担うことも多くあった。
ファーティマ朝はイスマーイール派の信仰規範を整備し、
シーア派王朝としての正統性を主張し、
サファヴィー朝も神秘主義教団から勃興して十二イマーム派をイラク、
イラン全土に浸透させ、
現在のイラン周辺のシーア派勢力の基盤を作った。
ムハンマドの子女の多くは早世し、
ムハンマドの血脈はファーティマを通じてのみ残されたため、
ムハンマドの血を引くことはハサンまたはフサインの子孫であることとほぼ同義である。
イスラームの中でもとりわけシーア派においては、
ムハンマドは無謬であったとされ、
アリーを含めた後継のイマーム達にもその無謬性は受け継がれたと見る。
そのためシーア派はスンナ派のハディースの内、
アリーがアブー・バクルやウマル、
ウスマーンに劣っていたとするハディース等 に関して、
スンナ派によりアリーからのカリフの位の簒奪を合法化するために偽造されたものとみなす傾向にある。
スンナ派の教義におけるアリー
スンナ派においてもアリーは預言者の娘婿であり義息として、
また4代目の正統カリフとして高い尊敬を受けている。
(加えて一部には、彼の息子ハサンを5代目の正統カリフとみなす見解さえある)しかし全体としてアブー・バクルやウマル、ウスマーンのカリフ位を認めるスンナ派は、
シーア派ほどアリーを高くは見ない傾向にある。
アリーをめぐる伝承と人物像
アリーの人柄を伝える資料は、ハディースや歴史書などで多い。
ここでは、スンナ派・シーア派を問わず、
そのような資料からアリーの人物像を扱ったものを紹介する。
アリーとアーイシャ
アリーとムハンマドの妻アーイシャは、
あまりそりが合わなかったことが伝えられている。
アリーは、アーイシャが砂漠ではぐれ、
ムスリム男性に助けられ合流した時、
アーイシャとその男性が砂漠で性交渉を行ったのではないかと非難する中心的人物の一人であった。
最終的にはクルアーンの啓示により、
アーイシャの無罪が確定したが(社会的に無罪が認められた)、
この事件はアリーとアーイシャとの間に亀裂を残した。
アリーはアーイシャに対して激しい憎悪を公然と表していたことで知られる。
駱駝の戦いの後アーイシャ側についたバスラ市民に対して『お前たちはその女(アーイシャ)の兵隊、四足獣(アーイシャ)の家来だった。そいつが唸るとお前たちはそれに応え、そいつが傷つくとお前たちは逃げたのだ。』 といい、
アーイシャ自身にも『なんとかという女(アーイシャ)はといえば、女特有の思考に捕らわれており、彼女の胸のうちには鍛冶屋の大釜のように悪意が燃え滾っているのだ。』と言及したエピソードが知られている。
また、アーイシャはアリーとムハンマドが話しているときに、
間に割って入りムハンマドを怒らせたという逸話もある。
アーイシャはアリーの名を口にするのさえ嫌がり、
その姿を見るのも我慢できないほどだった。
ウスマーンが殺害された後、
人びとがアリーをカリフに選出しようと決めたのを聞き、
「アリーがそうなる前に天が地につけばよい」と述べた。
アーイシャはアリーと対立し、
軍勢を指揮してアリーに対して反乱を起こし、
アリーが亡くなった知らせを聞いたときには平伏してアッラーに感謝したという。
父の日
イランでは、
アリーの誕生日であるヒジュラ暦第7月(ラジャブ)13日が、
父の日となっている。
その他
彼のみがスンナ派(スンニ派)、
シーア派の両方から公認されたただ一人の指導者である。
そのため、イラン・イラク戦争では、
スンナ派のイラク兵はアリーの肖像を「お守り代わり」に持っていたといわれる(シーア派のイラン人も「アリーの肖像」には銃口を向けられない。そのうえ、スンナ派自身の信仰にも反しない)。