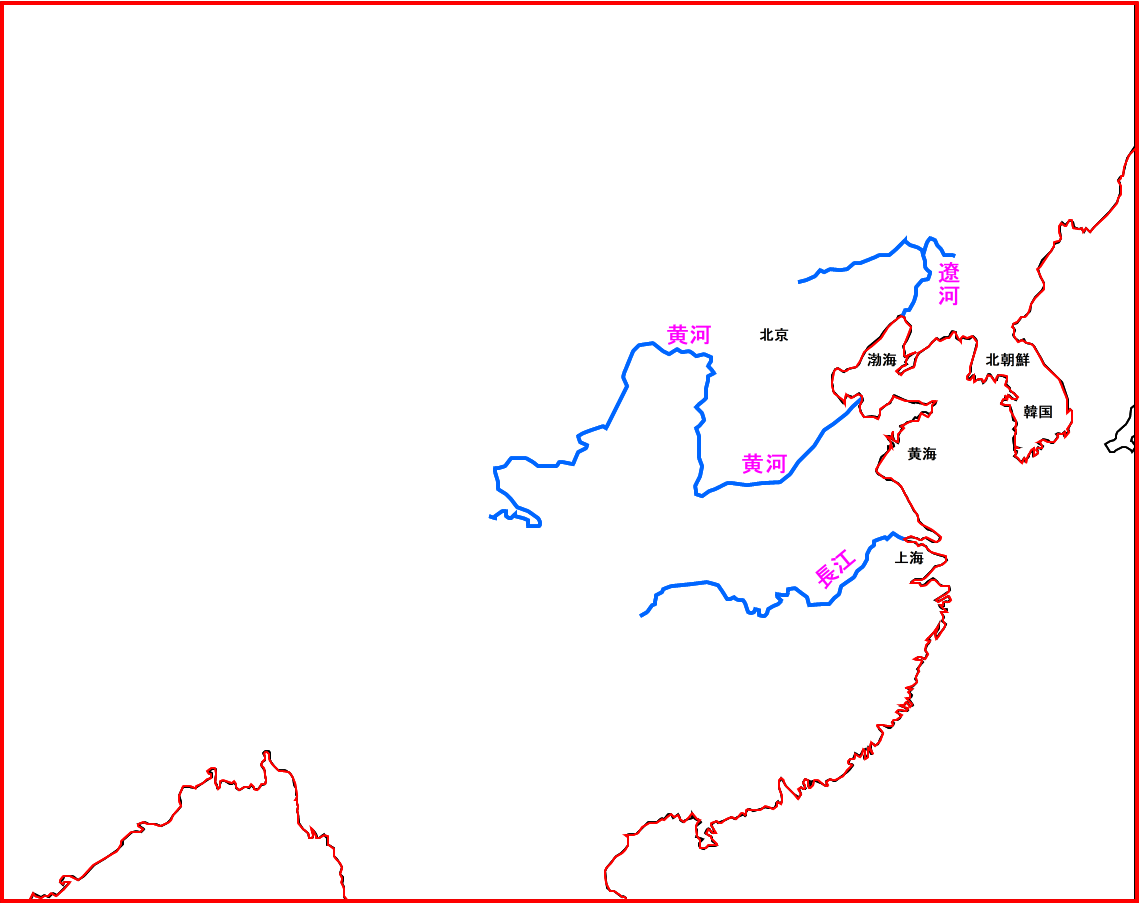小アジア / アナトリア / アナトリア半島
小アジア(アナトリアあるいはアナトリア半島とも言う)は、
西アジアの西端に位置する半島。
現在はトルコ共和国が支配するが、
古来、ヒッタイト、ペルシャ帝国、ローマ帝国、ビザンツ帝国、
セルジューク朝、オスマン帝国など大国がこの地で興亡した。
世界史上、小アジアはアナトリアとも言われ、
北を黒海、西をエーゲ海、南を地中海にはさまれ、
東にアルメニア、メソポタミア、シリア地方につながる地域を指し、
ほぼ現在のトルコ共和国のアジア側の半島部にあたる。
「アジア」とは本来、
ローマ時代に現在の小アジア(アナトリア)西部の属州の名前であったが、
次第にヨーロッパに対して東方世界全体を意味するようになった。
そのため本来のアジアを「小アジア」と言って区別するようになった。
アナトリアは本来半島の中心部の地域名であったが、
現在では半島全域をアナトリアと言うことも多い。
現在はトルコ共和国の主要な国土となっており、
トルコ語では「アナドル」と言っている。
注意:小アジアのトルコ化
小アジア(アナトリア)は現在のトルコ共和国であるが、 トルコ人はこの地に最初からいた民族ではないことに十分注意する必要がある。 アナトリアはかつてヒッタイト王国、リディア王国が存在し、 ペルシャ帝国、アレクサンドロス帝国、セレウコス朝、ローマ帝国の支配を受け、 4世紀以降は東ローマ帝国の領土となり、 次いでそれを継承したビザンツ帝国の領土として続いていた。 この間、ヘレニズム期からローマ時代まではほぼギリシャ文化・ローマ文化が支配的であり、 ギリシャ人の他、ユダヤ人も多く、 キリスト教が最初に広まったのもこの地域であった。
小アジア(アナトリア)は現在のトルコ共和国であるが、 トルコ人はこの地に最初からいた民族ではないことに十分注意する必要がある。 アナトリアはかつてヒッタイト王国、リディア王国が存在し、 ペルシャ帝国、アレクサンドロス帝国、セレウコス朝、ローマ帝国の支配を受け、 4世紀以降は東ローマ帝国の領土となり、 次いでそれを継承したビザンツ帝国の領土として続いていた。 この間、ヘレニズム期からローマ時代まではほぼギリシャ文化・ローマ文化が支配的であり、 ギリシャ人の他、ユダヤ人も多く、 キリスト教が最初に広まったのもこの地域であった。